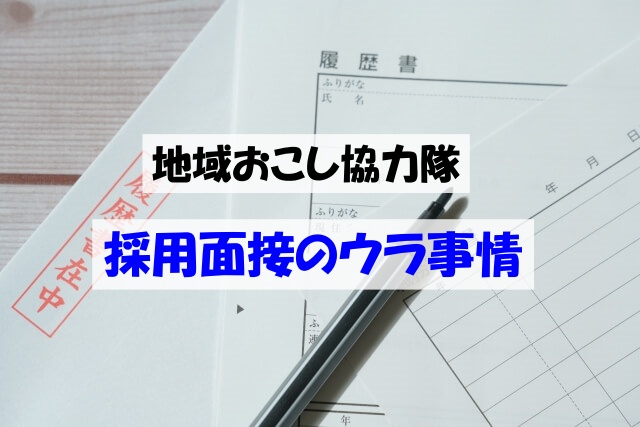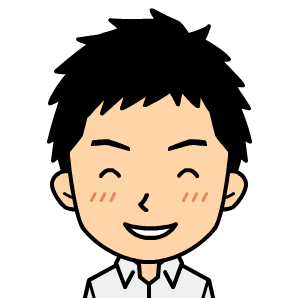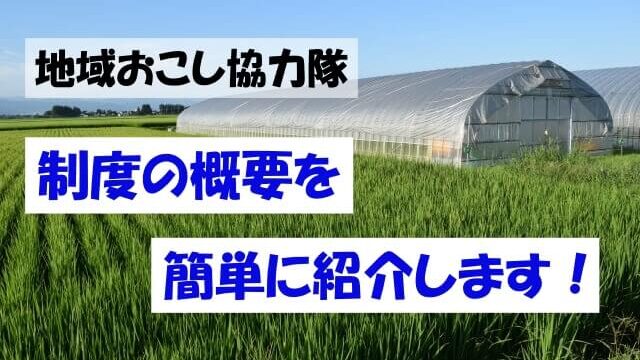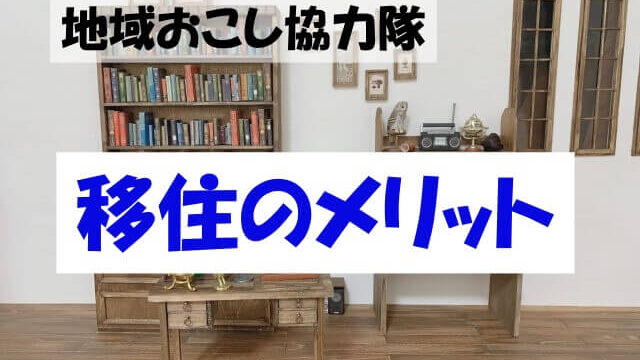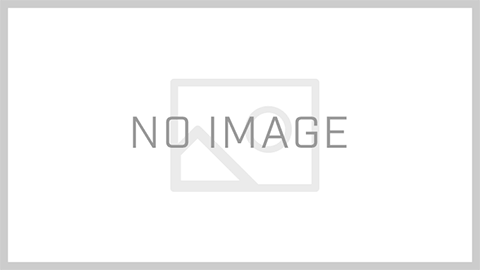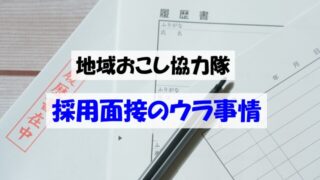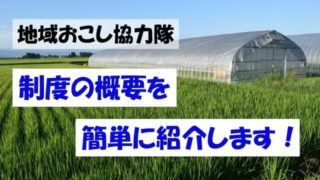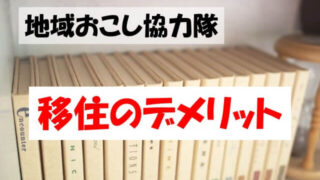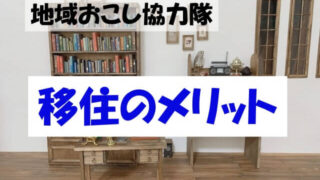・地域おこし協力隊の応募書類について、種類や書く時のポイント。
・地域おこし協力隊の採用面接の実態。
・地域おこし協力隊の面接での心構え。
応募してみたい地域おこし協力隊の募集があったのはいいけど、次のステップとして立ちはだかる壁が応募書類の作成と面接対策ではないでしょうか。
応募書類や面接対策をどのように準備したら良いのか分からない方も多いと思います。
通常の就職や転職と違って、誰かにアドバイスをもらえたりサポートを受けられるわけではないですからね。
そこで、地域おこし協力隊の応募・採用について、元自治体担当者の視点から、応募者が事前に知りたいと思うような内容をまとめてみましたので参考にしてください!
応募書類の内容・詳細
自治体によって応募書類は違う
地域おこし協力隊の応募書類は、各自治体が自由に設定しています。
多くの場合、募集要項に定めた応募条件に沿った内容の書類とその他に志望理由など文書の提出を求めるパターンが一般的です。
応募するために必要な書類は募集要項でしっかり確認しましょう。
以下が応募書類のオーソドックスなパターンです。
- 履歴書(応募用紙)
- 志望理由書、その他の文書
- 自治体独自の提出書類
それぞれ具体的に見ていきましょう。
履歴書
市販の履歴書の提出を求められる場合と地方自治体が独自に作った様式の履歴書の提出を求められる場合の2通りです。応募用紙などと書かれていることが多いです。
自治体が独自に作った様式の履歴書であっても記載する内容は市販の履歴書とほとんど同じです。
ただ特に必要ない記述内容や余白を削って、応募条件としている項目を満たしているかを記載できるように変更を加えています。
志望理由書、その他の文章
履歴書のほか、提出する書類として多いのが下記の書類です。
- 地域おこし協力隊を志望する理由(志望理由書)
- 地域おこし協力隊で活かせるこれまでの経験
- 地域おこし協力隊でやりたいこと
- 自分が思う地域活性化について
志望理由プラスその他項目を一枚または2枚程度で提出を求めれるパターンが一般的です。字数制限がある場合と特に設定されていない場合とがあります。
字数制限がない場合、記入枠が設定されている場合は記入枠に収まるように記載してください。
記入枠も特に設定されていない場合は、500~1000字程度を目安に作成しましょう。
字数制限がある場合はその制限内に収まるように文章を作成するのが一番無難です。
人道に反した内容や道徳的・モラルが著しく欠ける内容でない限り、書いた内容で直接採否が決まることはありません。
そんな中で、地方自治体が横並びの提出書類を求めるので、独自性を出すため奇抜な提出書類を求める地方自治体もあります。
よく見かけるのがパワーポイントで自己PRや自分の経歴・経験、地域おこし協力隊になってからやりたいことなどををプレゼンテーション資料として作成させ提出させるパターンです。
おそらく面接でこのプレゼンテーション資料を使用してプレゼンテーション面接のようなことをするのだと思います。
ただし、書きたいこと、アピールしたいことが多いのは分かるのですが、あまりにも字数が多い場合は、決められたルールを守れない人なのだなという印象を受けます。
字のキレイ、汚いは特に関係ありません。そもそもパソコンで作成する場合が多いと思いますが、未だに手書きを求めるところあります。
その他の書類
事前に住民票の提出を求めたり、会計年度任用職員の申込書の提出が必要な自治体があります。
自治体の会計年度任用職員の採用手順として、
会計年度任用職員の申し込み → 採用決定 → 任用(雇用契約)
の流れとなりますので、ただ単に面接前の申し込みの段階で、その手順を守っているだけに過ぎません。
この書類の提出を求めるのは、他の会計年度任用職員と同様の取り扱いとしているからです。
住民票の提出は、単に地域要件を確実に確認するために提出を求められるのだと思います。
採用が決まれば、少なからず現住所の確認は行われます。それを採用前にあらかじめ確認しておきたいという意向です。
応募書類を書く際に気を付けるべきこと
履歴書は事実をそのまま記載すれば大丈夫です。虚偽記載はウソだと分かると懲戒処分の対象となりますので、くれぐれも正直に記載しましょう。
また、地域おこし協力隊の採用にあたっては、定住する意思があるか無いかはかなり重要な要素となります。
人事の採用担当者が面接官として面接するわけではありませんので、面接官として面接に慣れていない人が面接を担当することがあります。
その場合は、応募書類に書いてある内容を額面通り受け取る可能性が高いです。
なので、自治体が用意した履歴書に、「任期終了後は定住する意思があるか否か」という項目があった場合、迷わず「定住します」と記載してください。
いわゆる踏み絵みたいなものです。
1~2回の面接と提出された書類だけで採否を決定する場合が多いですので、提出する書類は、面接だけでは分からないあなたの人柄を見ていると考えてください。
行政機関は文書を重んじる世界ですので、提出する書類からあなたという人物を見ています。
もちろん面接も重要ですが、面接の前にあなたと自治体とが初めて接触する媒体が応募書類ということになりますので、気を抜かないようにしっかり準備しましょう!
書類選考で落ちることはあるのか
これについては、各自治体の採用方法によるので一概にこうだとは言えませんが、元担当者として参考までに意見を書きたいと思います。
公務員になるための公務員試験は、年齢制限はあるものの、ある一定の基準を満たした人は全員面接に呼ぶ、という機会の平等を重視する傾向にあります。
ある一定の基準とは、筆記試験で「何点以上の点を取った人」などをイメージしてください。
これををそのまま当てはめて考えるといいと思います。実際にこのような考え方をする自治体職員は多いです。
つまり、募集情報で決められた応募書類をキッチリ提出されしていれば、
- どう見ても読めない文字
- 内容に明らかなウソがある
- 明らかにふざけて書いていることが読み取れる
- 募集要項で指定したルールを守っていない
などことが無い限り、書類選考で落とされることはあまりないと考えて良いでしょう。
採用面接の内容
採用面接の詳細は自治体によて違いますが、事前に準備する際の参考にしてもらえればと思います。
面接日の連絡
地域おこし協力隊の応募書類は、募集情報が公開されて1~2カ月後に提出期限を設定していることが多いですので、そのほとんどは締め切りギリギリに届きます。
担当者としては、届いた順番に、
- 応募書類が形式的に揃っているか、
- 地域要件を満たすか、
- その他募集情報に記載した応募条件を満たすかどうか、
を確認します。
特に、地域要件はかなり念入りに確認します。
これらの応募条件等を満たしていない場合であっても、すぐに不採用通知を送るのではなく、一度組織内で決裁を取り、どのように対応するかを決めます。
また、地域要件を満たさない場合は速攻で不採用確定なのですが、その場合でも、通知を送る方法や不採用とする理由をどのように記載するかは検討します。
連絡手段はメールや電話連絡、文書送付など、自治体のスタンスによって違うでしょう。
また、面接日時についても、決め打ちの場合もあれば、応募者と調整のうえ決める場合もあります。
そして、その旨を募集要項に記載してくれている自治体もあれば、何も記載されていないところもあります。
担当者としては、履歴書にメールアドレスを記載するところがあったので、「メールで連絡すればいいのにな」と思っていましたが、募集開始~採用までに時間的余裕がなく、早く面接スケジュールを組む必要があったため電話での調整を行っていました。
ちなみに、面接スケジュールは面接官の都合を考慮して決めなければいけませんので、担当者としては、まず面接官全員に面接が可能な日時を聞いて、仮にスケジュールを押さえて、応募者に候補日を電話で伝えて都合を聞いて・・・とかなり大変でした。
面接官は誰がするのか
主に自治体の職員、受け入れ団体(「中間支援団体」などと呼んだりします。)の責任者や担当者、地元住民代表者などが面接を担当します。
それに卒業した元協力隊員や現役の先輩協力隊員が加わるケースもあります。
面接官の人数は様々ですが、行政、地元住民のバランスを取ると大体5~7人となる場合が多いようです。
面接時間と面接回数は
面接時間は30~40分程度。
面接回数は1~2回です。1回の場合が多いです。
そして、通常の面接とは別に、面接日に現地見学や座談会(面接の前後に実施する砕けた形の意見交換会みたいなもの)など、独自の選考を行っているところもあります。
採用面接では何をみているのか
協力隊員に期待していることなど、何を目的として募集しているのかによって評価されるポイントが変わってきます。
全国的な採用基準が決められているわけではありませんので、何を重視するかは採用側の自由です。
元担当者の立場から、採用面接では何をみていたのかということをお伝えします。
私の自治体では、面接は、統一項目をそれぞれの面接官の視点で評価してもらう観点から、評価シートを作成して面接官に記入してもらっていました。
その評価シートでは様々な評価項目を設定して採用者を評価していましたが、最終的な評価ポイントを集約するとこのような感じになります。
- この地域でやって行けそうか、馴染めそうか
- このまま定住してくれそうか
- 地域活動に参加してくれそうか
活動内容が特殊な場合や何か特別なスキルが必要とされる場合は、これにさらにプラスの項目を設定するような感じです。
結局、採用面接における質問内容もこの点を中心に聞かれることになると考えておいて良いでしょう。
採用、不採用の決定の裏側
割といろんな場面で見られている
自治体担当者と接触した段階から実質的には面接が始まっていると考えた方が良いです。
担当者レベルでは最終的な採否に加わることは少ないですが、上司から印象を聞かれたり、余程目に余る行動を取った場合などは上司に報告することはあります。
また、規模の小さな自治体では、そもそも最終判断する権限をもった職員が最初から担当者的なポジションで採用面接をする場合もあります。
外形的には誰が決定権を持っている分かりませんので、気を抜かないようにしてください。
採用を決定するのは誰か
基本的には面接の際の評価に基づいて合議制で決定されると考え良いでしょう。
ただし、ひとりの面接官が強く反対したり、自治体職員が面接官の場合は、より上役の上司が強く反対したりした場合は採用を見送ることはあります。
また、逆に、地域代表として面接官をした人が強く推せば採用されたりなんてこともあります。
つまり、実際は、面接官の微妙なパワーバランスや考え方に左右されることが多いというのが実情です。
この点は、応募者はどうしようもありませんので、過度に気にしなくて良いです。
最終的に
採用されるかどうかは、その時の募集人数と応募者数に大きく左右されますので、応募するタイミングによって運の要素もあります。
私が担当者していた時の話ですが、
2名の募集に対して15人の応募者があった時には、2人以上採用したいという地元からの申し出があり、さらに採用したいと思えるような人材が2名以上いたにも関わらず、2名分の予算しかないとの理由から採用をしたのは2人のみでした。
自治体の予算の都合上、残念ながら、予定していた採用者を増やすことが出来ません。
自治体は、前年度に当年度の予算を決めるため、何か特殊な事情がない限り、民間企業みたいに融通を利かせることがどうしても出来ないのです。
特殊な事情とは、予算編成を行った際(前年度中)に予期できなかった事情が突発的に発生したなどです。自然災害が起きて復旧に予算が必要になった場合などをイメージすると分かりやすいと思います。
地域おこし協力隊の採用予定人数というのは、この特殊な事情だとみなされることはほとんどないと言い切ってしまっても良いと思います。
逆に、1名募集に対して応募者が1名しかいなかったという場合、必ず採用されるかというとそうでもありません。
まとめ
今回は、応募書類の提出から採用面接の裏側までを解説しました。
選考方法については、一般的な就職・転職活動とだいたい同じで、
書類選考 → 面接の実施
という基本的な流れは変わりません。
しかし、評価されるポイントは違います。
一般の就職・転職とは異なり、会社・組織に貢献してくれるか、職務遂行する能力はあるか、など視点ではなく、定住してくれそうか、地域に馴染めそうかなのどの視点が重視される傾向があります。
地域おこし協力隊に応募する際には、その点を意識して応募書類、採用面接に臨んでみてはどうでしょうか。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。